電子情報通信学会 通信ソサイエティマガジンB-Plus 2012冬号 No.23[書籍]
電子情報通信学会が出版している通信ソサイエティマガジンB-Plusの中に、「今時のアマチュア無線」を特集した号がありました。「日本のアマチュア通信の歴史と世界の現状」という記事に始まり、非常通信、社会貢献、無線機の動向の記事もあります。
 (※)
(※)これからハムを始めようという方には、「アマチュア無線を始めるには」という記事もお勧めです。
学会誌だけあって記事の内容は充実しており、この号以外にも、無線通信に関する特集をした号がありますので、バックナンバーを探してみるのもよいかもしれませんね。
電子情報通信学会では、通信ソサイエティマガジンB-Plusの2015 年春号(32号)から、電子版を完全無償で公開するようになり、バックナンバーについても無償で公開することを公表しています。
(2015年12月、2018年5月追記)
- 通信ソサイエティマガジンB-Plus [電子情報通信学会]
- バックナンバー [電子情報通信学会]
- 2012冬号 No.23 小特集「今時のアマチュア無線」 [PDF 25.3M]、 訂正記事 [PDF 0.7M]
- 2014冬号 No.31 小特集「今時のラジコン無線技術」 [PDF 26.4M]
- 2018春号 No.44 「国家資格の概要と意義(通信)」 [PDF 1.8M]
- 電子版無償化のお知らせ [電子情報通信学会]
Morse Code Trainer [Android用アプリ]
モールス信号を学習するためのAndroid用アプリの中で使い続けているのが、この「Morse Code Trainer」です。よく似た名前のアプリがあるので、アイコンのデザインで識別してください。気に入っている点は、
(1) 送信練習ができること
(2) 自動で設定される5文字×3で構成された受信練習ができること
(3) イヤホンさえあれば、電車の中でも送受信練習ができること
です。
なかなか、送信練習を簡便にできるアプリにたどり着けなかったのですが、このアプリはこの点において期待どおりのものでした。
送信練習では、画面下部に白い長方形で表示される領域をタッチし、そのタッチ時間を調節することで長点、短点を実現できます。文字(Letters)や単語(Words)練習モードでは、表示された文字通りにモールスコードを入力すると、文字の色が変わります。自由入力(Free Pad)モードでは、入力した符号に対応する文字が表示されていきます。
学習用に特化したアプリですので、モールス信号の解読機能は備えていません。
「お空で『--... -- .---- - .-- -.』なんて聞いたことがないぞ!」という突っ込みが入りそうですが、その理由は専ら当局の学習能力の低さと電鍵がないという根本的な問題によるもので、このアプリの限界を示すものではありません。インストールからもう半年以上経っていますが…。
(2015年9月)
アマチュア局の非常通信マニュアル [文書/サイト]
ハムの皆さんにとって、非常時における通信は、無線従事者試験で扱われるトピックの一つであると同時に、先の東日本大震災の発生を受けて、現実の問題として考えさせられることになったトピックではないでしょうか。このマニュアルは、非常通信の運用やそれへの備えについて平易にまとめられた、JARLならではの文書だと思います。非常通信に限らず、一般的な災害対策のための読み物としても十分な内容です。
東日本大震災直後の通信手段の確保に関する成果や教訓がまとめられた資料ができれば、より一層、備えが増すかもしれませんね。
(2013年2月)
Ethics and Operating Procedures for Radio Amateur (Edition 3) [文書/サイト]
ARRLのサイトで見つけた文書です。この文書には、アマチュア無線における運用の決まりごとがまとめられています。28か国語に翻訳されているそうで、日本語では第2版を見ることができます(邦題:「アマチュア無線の運用倫理と運用手順」)。運用の初歩は知っているつもりでしたが、読んでみますと新たな発見があるとともに、不適切なものとして説明されている事例が、現実の運用において多く聞かれることに気付かされました。筆者は、「QRZ」と「over」の誤用に強い懸念をお持ちのようで、正しい用法について繰り返し説明しています。また、コンテストや電信での運用についても記載されていますので、これらへのチャレンジを予定の皆様にも一読をお勧めします。ところで、皆さんは、コンテストでのCQを出す際に、最後に「コンテスト」と言う理由をご存じですか?
筆者は、この趣味が外国語を学ぶ良きツールであるとも述べています。QSOを想定してのことでしょうが、様々な言語で書かれたこの文書を読むのも、その学びの一環になるかもしれませんね。
(2013年1月、2019年12月リンク修正)
- HAM Radio Ethics and Operating Procedures
- Ethics and Operating Procedures for Radio Amateur (Edition 3) [PDF 2.1M]
- 各国語バージョンの掲載サイト
- (日本語)「アマチュア無線の運用倫理と運用手順」(1)、(2) (CQ ham radio 2009年8月号別冊付録)
- ARRL - Operating Ethics
Ham Radio For Dummies[書籍]
書籍のタイトルを日本語に訳すと「サルでもわかるアマチュア無線」といったところでしょうか?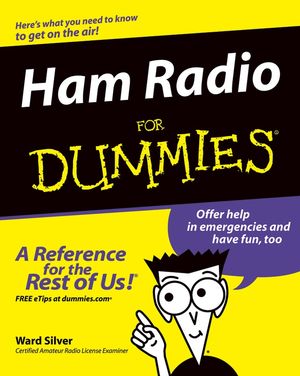 (※)
(※)アメリカのハム向けに記述されていますので、免許制度やレピータの利用形態など、日本と異なる点もありますが、このような相違点自体も楽しむことができると思います。非常時における通信に関する記述では、日本でも参考になるところもあるように思いました。
英語というハードルはありますが、DXを楽しまれる際の表現を勉強すると開き直って、ご覧になるというのはいかがでしょうか?
- Ham Radio For Dummies [Dummies.com]
- 目次
- 抜粋見本(第1章) [PDF]
- ボーナス章 [PDF]
- アマチュア無線関連のウェブサイト・リンク
TDK Techno Magazine[サイト]
コモンモード・ノイズについて、ネット上で調べているうちにたどり着いたサイトです。技術情報が、読み物的に且つ図面を多用して、とてもわかりやすく掲載されています。最初に読ませて頂いた記事は、「なるほどノイズ(EMC)入門 1」という記事でした。この他にも、フェライトコアに関する記事なども掲載されています。皆さんがご関心の記事はありますでしょうか?-----
(※)印を付した著作物の著作権は当局には帰属していません。





0 件のコメント:
コメントを投稿